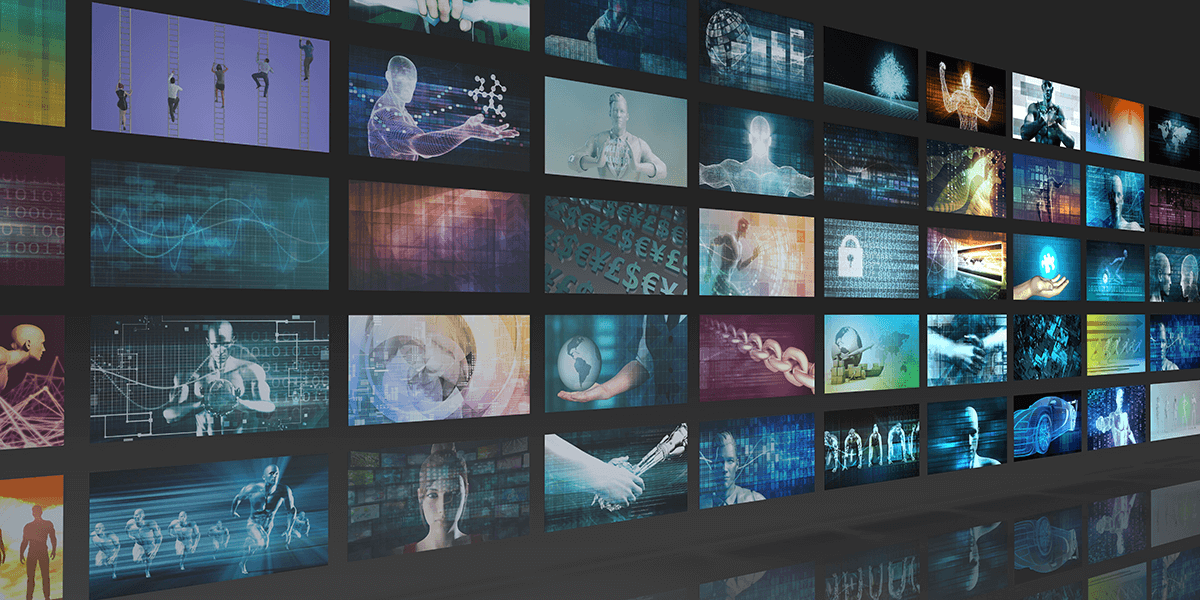話題のヒット商品やサービスを送り出したビジネスリーダーへのシリーズインタビュー。
成功の裏側にある戦略やマネジメントについて『洞察力』という切り口から掘り下げ、ビジネスを成功に導く本質に迫ります。
外部の視点を取り入れなければ成長の機会は失われてしまう。
自分の「外」にあるものとの「会話」を大事にする
鈴木健の洞察力(後編)
「閉じた系」に成長はない。拡張するスポーツカテゴリーでニューバランスは何を考えているか

写真左)株式会社 ニューバランスジャパン マーケティング部 ディレクター 鈴木健様
写真右)弊社 コンサルティング本部 インサイトコンサルティング部 コンサルティングディレクター 堀
スニーカー市場で存在感を発揮するニューバランス。近年は「アスレジャー」ブームなどで「スポーツ」がカバーする市場は拡大傾向にある。そうした市場において、これからのニューバランスは何を目指していくのか、前回に引き続き、鈴木健氏にお話を伺います。
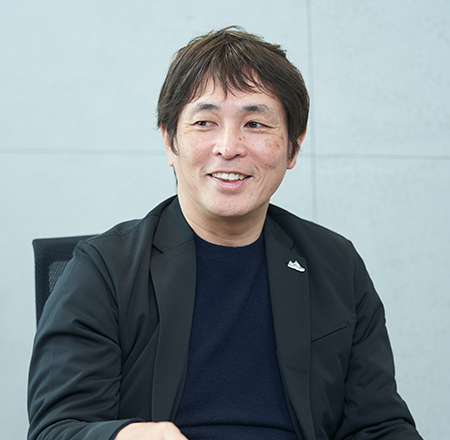
株式会社 ニューバランスジャパン
鈴木健様
マーケティング部 ディレクター
1991年広告代理店の営業としてスタートし、ナイキジャパンで7年のマーケティング経験を経て2009年にニューバランスジャパンへ。
ブランドマネジメントやPR、広告などマーケティング全般のほか直営店やEC事業責任統括も務める。
「隙間」を埋めていく日本企業のブランド管理は独特
堀 ニューバランスはグローバルブランドですが、日本とその他の国でマーケティング戦略に違いはあるのでしょうか。
鈴木様 組織的な話をすると、事業部が多い会社は縦割りの組織体系になっており、組織間の隙間が多いため、今までとは異なる方法で市場にアプローチするという機会がすり抜けてしまうようです。先日も、とある企業の方と日本の会社は割と隙間を埋めるのが得意なのではないかという話をしたことがありました。
外資系や海外を起点にしている企業は複数のブランドを展開していることが多いですが、それぞれのブランド領域が決まっているため、その領域外に展開することはありません。一方、日本では核になる商品がブランドのように存在していても、そこから派生する商品もたくさん販売しているケースが多いです。そのようなメーカーは「親ブランド」「子ブランド」と表現しますが、ブランド管理としては日本独特な考え方になります。
この管理の利点は隙間がないことです。ハウスブランドでは領域が決まっていて、その機会をうまく活かすために、ブランドを拡張するのではなく新しいブランドを立ち上げるのが外資系です。日本の場合は、商品開発の際にスーパーマーケットの棚で新しく売上げを伸ばすためにはどのようにすべきか、から発想するので隙間がありません。同様に、自動車でも棚を埋めるような感覚で新車を作るので隙間がなくなります。先日お話をした方は「カニバリは気にしない」ともおっしゃっていました。
外資系の企業は社内競合よりも市場機会の方を重視しているため、グローバル視点では大きなブランドであってもチャレンジャーのようなことをやっているわけです。日本企業は事業ごとに売買しないため、ブランドを売却することはあまり多くありません。その理由としては、事業やブランドの結びつきが強いため、売却できないのです。

堀 確かに日本企業の場合、事業を撤退するときに譲渡という形はあっても、事業を継続中にブランドを売買するということはあまり聞きませんね。
鈴木様 リソースを違う形で使っているのでしょう。海外は領域が大切という考えなので売買ができる。日本の企業でも売買はありますが、ただ日本企業がそうした海外のブランドを取り込むと全く違う形になったりします。日本企業はブランドとマーケティングが密接に関係しているため、単純に成功事例のマネはできないですし、グローバルブランドも生まれにくいです。
過去のモデルをアレンジした「復刻」で新規層へのアピールにも成功
堀 「327」というモデルではベネフィットを見直してヒットにつながったそうですね。
鈴木様 その話には前段があって、私たちも出来れば新しいフランチャイズや商品を作りたいという思いはありましたが、新たにゼロから作るよりも、過去のモデルを活用してストーリーをうまくアレンジした方が良いと気づいたのです。全てが成功したわけではありませんが、327はよい結果を残した事例のひとつです。
過去のモデルからの復刻というと、マニアはオリジナルに忠実であることを求めます。それでは今の消費者が求めるニーズからは外れてしまいますし、品質面でも問題があります。327は70年代のオフロード用シューズなので、ソールに突起があることが特徴ですが、全体的な見た目は薄いシューズでした。オリジナルの特徴を踏襲しながら、今のトレンドであるミッドソールを厚くして作りました。復刻のパターンとしてはルール破りでしたが、そこがウケたことで面白い事例になりました。
堀 旧来のファンにも受け入れられたのでしょうか。
鈴木様 通常の復刻は既存のお客さまにしか受け入れられない傾向にありますが、この327はデザインそのもので新しい層に受け入れられました。

堀 スポーツ系ブランドはトップアスリートとの契約も多いですが、広告塔となるトップアスリートにはどのようなことを期待していますか。
鈴木様 自社が手掛けているスポーツカテゴリーでプレーするアスリートと契約するのがベーシックな選択ですが、私たちは同じカテゴリーでプレーしているという以上の価値や資質を持った存在であるという認識から、アスリートの見せ方は常に考え続けています。
期待する役割としては、自社ブランドはスニーカーのイメージは強いものの、スポーツシューズのイメージが弱いので、それを代弁してほしいということと、ブランドの市場シェア拡大につながってほしいと思っています。
堀 競技面の成績だけではなく、人間性も含めて期待値があるということでしょうか。
鈴木様 トップアスリートはその競技における実績だけではなく、スーパーヒーローのような印象もあるので、それらをニューバランスというブランドにも当てはめたいと考えています。

どこに「機会」があるのか、スポーツカテゴリーで意識するものは
堀 今後、ブランドの成長をどのような視点で評価し、そのためには何が必要だと考えていますか。
鈴木様 ニューバランスのビジネスドメインはスポーツやフットウェア、アパレルが属するマーケットなので、その中でのポジションを高めることです。スニーカーは強いものの、シューズ全般やアパレルは、スニーカーほど拡大はしていません。
マーケットサイズから見ると、スポーツカテゴリーは成長産業として見られています。昔の高齢者は革靴を履いているイメージでしたが、今後はどの世代もスニーカーを履くようになるくらい世の中がカジュアル化していて、全世代が消費者となりうると認識できるようになってきています。
もう一つ、スポーツカテゴリーはテクノロジーの進化によるベネフィットを受けやすいというところがあります。オリンピックなど世界的なスポーツイベントはその魅力をアピールする場としてテクノロジーの進化を促進しています。ファッション業界では一定のサイクルで流行が繰り返されていますが、スポーツ用品は機能などが少しずつ改良されて、各アイテムの役割も拡張してきています。
その一例として世界的なトレンドになった「アスレジャー」があります。ビジネスシーンで着られているストレッチ素材のセットアップやシャツもスポーツ用の素材が使われています。ですから、スポーツカテゴリーは「スポーツ」の意味が変化することでその変化に応じて拡大していく可能性があります。
堀 スポーツよりも生活習慣に近づいていくようなイメージということですね。
鈴木様 コロナ禍中も含めて、この数年で一番伸びたのはアウトドアブランドです。山登りなどのアウトドア自体が、ウェルネスやアクティブな活動の延長線上にあります。近年、スポーツブランドがアウトドアに進出しているのは、スポーツやアクティブなものとしてカバーする領域が広がっているからですね。それは、山登りやハイキングなど特定の行動だけではなく、健康的に過ごしたいという意識も含まれるので機会はとても多いです。ニューバランスというブランドがその市場に参入する余地があるのであれば、今のスポーツカテゴリー内で競争するよりも、アスレジャーに目を向けた方がいいと考えています。
その視点でみると、今のスポーツ市場は10代の男性が中心ですが、今後はシニア女性のように従来のパーセプションではない人が対象になると考えられるためマーケットは拡張するはずです。これはエンドースメントの話にもつながります。「スポーツ」という概念が変化・拡大することで、それに対して意味のある象徴的な存在は誰になるのかを考えるようになります。この場合、老若男女が好感を持ち、健康的でアクティブな人で、イメージとしても強制的にスポーツをさせるような人ではなく、むしろオープンに招き入れてくれそうなタイプの人がフィットすると思います。

堀 セグメンテーションの話にも通じるところですね。競技スポーツとスポーツウェルネスの間をうまく埋める方法を考えないといけないということでしょうか。
鈴木様 そうですね。競技スポーツが大事なのは、その競技がエンターテイメントとして成立しているときで、その競技スポーツを見ている人が面白いと感じるかどうかが重要です。
競技スポーツは興味のある人だけが見ているイメージがありますが、オリンピックはマイナーな競技を知る重要な機会となります。オーディエンスとして見て楽しいし、今まで知らなかった競技に触れるきっかけとして機能していると思います。
だからスポーツカテゴリーとしては大会や試合ではないエンターテインメントがあっても良いのではないかと思います。野球の地上波民放のテレビ中継も減っていますし、サッカーも有料サービスに加入しないと見られない環境になっています。そこにスーパースターやヒーロー的な存在が登場することで多くの人が触れる機会となり、マーケティングとしても広告効果が評価されるのですが、現状はそのようにうまくいくことは少ないと思います。これはセグメンテーションの悪い面が出ていて、有料サービスでも観たい人からお金を取るシステムになっていることが原因として考えられます。効率はいいのかもしれませんが、マーケットは小さくなっていくので成長への期待は薄いです。
組織をうまく動かすためには、上に立つ者の振る舞いが重要
堀 鈴木さんはビジネスリーダーとして組織をまとめる立場にあります。組織を円滑に運営するためにどのようなことを意識していますか。

鈴木様 私もいい方法があれば教えてもらいたいです。皆さん上の人を見て、自分の行動を決めていくところがあるので、上に立つ立場の人の振る舞いは結構大事だと思っています。セグメントの話でも「狭いところをしっかりやればいい」と言う人の下では狭いところしか見なくなるので、機会を広く見るように、上に立つ人が言わないといけないと思います。
あとは、「今、評価されること」ばかりをやっていても成長はない。すぐに役立たないことだとしても、周囲と違うことにチャレンジしている人を簡単に批判するような組織では成長する機会を逃してしまいます。ビジネスを守るという意味では目先の成果も必要なので、組織内の多様性を維持しながら先導することを考える余地を持つことは大切なのではないでしょうか。
堀 歴史のある企業やブランドでは一層チャレンジすることの難しさがあると思います。チャレンジさせる余地を生むような文化を作るために心がけていることはありますか。
鈴木様 「閉じた系」には成長がないと思っています。「閉じた系」とは、ある「系」の中では全てが正しく行われているのだけど、その中には「系」の外にある意思決定でしか解決できない命題がある。だから「閉じた系」の中でルールを守るばかりでは意思決定ができなくなる、というパラドックスがあるという話です。
常に、自分が所属する組織とは異なる視点、つまり「外部」の存在が必要です。消費者もそのひとつですが、「外部」の視点を取り入れていかないと成長の機会を失ってしまう。今の自分にとって「外部」はなんだろうかと常に意識しています。関係ないと感じるようなことでも、意外と自分を取り囲んでいるもののひとつならば、それが重要なことなのです。
身近な例だと、仕事も家庭も大事というときの「家庭」は外部ですね。休みの日に仕事をしてもいいかどうかというのは仕事の「系」の中では決められない。パートナーが止めろと言うなら考えざるを得ない。これが外部。それと一緒です(笑)

堀 この連載ではビジネスリーダーの皆さんに「洞察力」についてお聞きしています。鈴木さんにとって最も大切な洞察力は何でしょうか。
鈴木様 今の話にも通じますが、やはり外との会話は大事です。「会話」といっても、人との会話である必要はありません。どこか新しい場所へ行くことも会話のひとつです。自分が経験したことのない環境にいきなり放り込まれると違うことを考えますし、今、インタビューを受けていることも、話をしながら「そうだったな」と思い出すのも経験になります。聞かれたことで普段考えていなかったことに気づくことができるのが「外」との会話です。
私にとっては読書も会話だと思っています。好きな本を何度も読む。それは本の中身を知りたいからではなくて、経験をなぞるようなイメージです。読んだ本に何が書いてあったか、詳細に思い出すことは難しいけれど、読んだという経験は残る。実は、本を読むことで得られるのは知識ではなく経験だと、私は感じています。
知識が必要なのであれば、そのときに本を取り出せばいいので読まなくてもいい。だけど、読むことは経験になるので、今の自分にはどのような経験が必要なのかを考えて、読むべき本を探した方がいいと思います。皆さんも経験を意識すると読む本は決まっていくと思いますので、経験を大事にして本を選ぶと、良い本に出会う可能性も高まるのではないでしょうか。
堀 「会話」や「読書」など身近な経験も含めて外部との対話を怠らない、それによって「閉じた系」にはない成長を自分達の中に取り込むことが大切ということですね。本日はお時間をいただきありがとうございました。