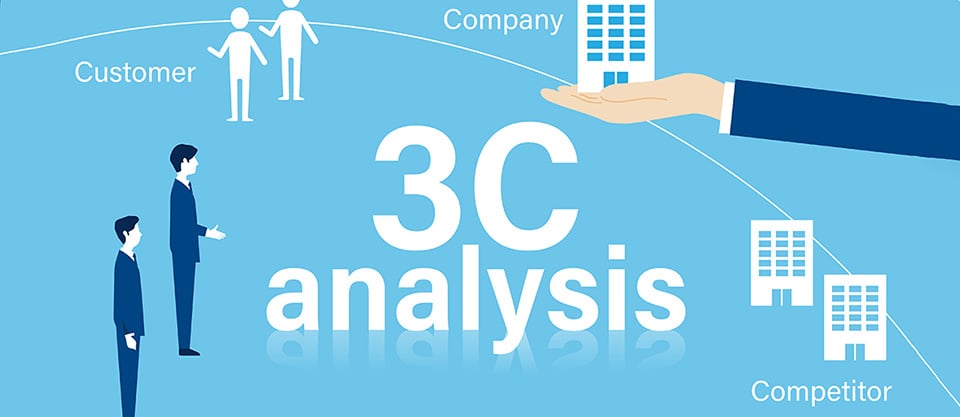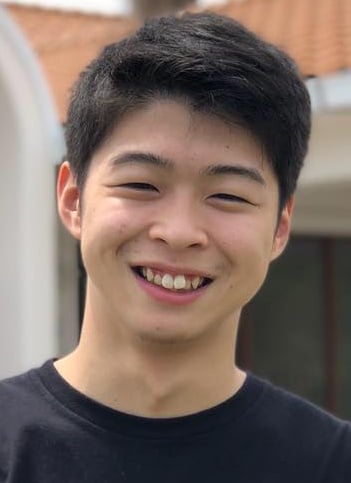マーケティングにおけるカニバリとは?デメリットや原因、防ぐポイントも解説
公開日:

自社の商品やサービス同士が競合化してしまうことをカニバリゼーション(カニバリ)といいます。事業の資源を有効活用するために、このような事態は、ぜひとも避けたいところです。
今回は、カニバリがどのようにして起こり、どういうデメリットをもたらすのかについて詳しく解説します。具体的な対策も紹介するので、マーケティングやディレクションの現場ご担当者はぜひ参考にしてください。
カニバリとは
カニバリは、「カニバリゼーション(Cannibalization)」から生まれた略語で、日本語に直訳すると「共食い」「食い合い」を意味します。ビジネスにおいては、自社の異なる商品やサービスが、同じ市場でシェアを奪い合ってしまう現象を指し、その状態を「カニバる」とも表現します。
本来であれば類似セグメントでシェアを競う競合他社に対し、有効なマーケティング施策で優位性を示さなければなりません。しかし、戦略を誤ると自社の商品やサービス同士でシェアを競う「共食い状態」になってしまいます。
ターゲットが同じだったり、機能が似通っていたりする商品を複数出すと、往々にして、同一企業内でカニバることになります。新製品投入だけではなく、出店のロケーションやプロモーションの時期などでもカニバリは発生します。

カニバリのデメリット
カニバリには、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。カニバリのデメリットについて解説します。
経営資源の奪い合い
カニバリの主なデメリットは、経営資源を自社で奪い合うことになる点です。
本来であれば、他社との差別化のために使いたいリソースを、自社のライバル製品のために使う状況に陥ります。カニバリが起こると、自社でつぶし合うことになり、経営資源の無駄遣いとなってしまいます。
競合他社との競争力低下
経営資源が枯渇することにより、競合他社に対する競争力が弱まるだけでなく、マーケット開拓の機会損失が生まれます。また、競合他社にマーケットでの優位性を明け渡してしまう可能性も高くなります。
本来であれば類似セグメントでシェアを競う競合他社に対し、有効なマーケティング施策で優位性を示さなければなりません。しかし、カニバリが起こると、総合的な集積性が伸び悩む結果になるでしょう。

カニバリが起こる原因
そもそもカニバリは、なぜ起こってしまうのでしょうか。カニバリが起こる原因について解説します。
ターゲット層の読み間違い
カニバリゼーションが発生する原因としてもっとも多いのが、ターゲット層の読み間違いです。消費者のニーズを十分に分析せず、既存商品と似たターゲット層を対象とした新商品を開発することにより、同じ市場内での競争が激化するのです。
例えば、飲料メーカーが既存の「カロリーオフ」を謳う製品に加え、「糖質オフ」を打ち出した新製品を投入した場合、健康志向の消費者が両者の間で分散し、それぞれの売上が伸び悩む可能性があります。
ターゲット層の適切な設定は、マーケティング戦略の要です。
ドミナント戦略の失敗
「ドミナント戦略」は、特定の地域内に集中して店舗を展開することで物流の効率化やブランド力の向上を図る手法です。
しかし、この戦略には注意が必要です。なぜなら、同一エリア内で店舗が過剰に増加すると、商圏の重複が生じ、既存店舗と新店舗が顧客を奪い合う、すなわちカニバリ状況に陥る可能性があるからです。
例えば、ある都市部で新たに複数店舗をオープンした場合、人口密度に対して店舗数が多すぎると、個々の店舗の収益性が低下します。ドミナント戦略は、成功すれば圧倒的な市場シェアを確保できますが、適切な需要予測と競争分析が欠かせません。
カニバリを防ぐには
カニバリを防ぐ具体的な対策として、「ターゲットの差別化」「商品やサービスの差別化」「社内の情報共有」「コストバランスの調整」の4つがあげられます。
これらの対策は、経営マーケティングやデジタルマーケティングなど、あらゆるマーケティングに効果的なので、カニバリに悩んでいる現場ご担当者はぜひ参考にしてください。

ターゲットの差別化
商品やサービスのターゲット層が重複・類似しないよう、あらかじめペルソナを明確に設定した上で商品やサービスを設計・開発すると、高い確率でカニバリを防ぐことが可能です。
カニバリを防ぎやすくなるだけでなく、マーケット拡大の商機を見出しやすくなったり、自社へのニーズをより明確に把握しやすくなったりするメリットもあります。自社商品・サービスのブランドや世界観を守りつつ、カニバリ防止に配慮しながらターゲットをいかに適切に設定するかは、マーケターの腕の見せ所です。
既存商品・サービスとの差別化
類似した層がターゲットにならないよう、それぞれニーズやコンセプトが異なる商品を展開し、各商品・サービスの明確なポジショニングを図るのも、カニバリを防ぐのに効果的な手段です。
具体的には、ターゲット層の違いや商品コンセプトの差別化を図り、それぞれの商品が消費者に異なるメリットを提供できるように設計します。例えば、同じ飲料メーカーが提供する製品であっても、「健康志向」を強調した製品と「リフレッシュ感」を重視した製品があれば、それぞれ異なるニーズを持つターゲット層に訴求できます。
また、価格帯を明確に分けることも有効です。高級志向の商品と手軽に購入できる普及版の商品が混在しても、カニバることは少ないでしょう。
社内の情報共有
カニバリを防ぐためには、社内で効率的に情報を共有することも大切です。ある程度の事業規模にある場合は、情報共有を効率化するために、ナレッジマネジメントシステム(KMS)などの導入を検討しても良いでしょう。
ナレッジマネジメントは、組織内での知識や情報の共有と管理を通じて、カニバリを防ぐための重要な方法です。マーケティングや商品開発、サービス提供の各プロセスで得られた知見を社内で共有することで、各プロジェクトに重複や矛盾が発生するのを防ぎます。
例えば、新商品を開発する際に、既存の商品情報やターゲット層のデータを適切に活用すれば、ターゲットの重複や競合する商品設計を回避できます。また、他部署の知見や経験を活かすことで、より洗練されたポジショニングが可能となり、カニバリゼーションのリスクをいっそう軽減しやすくなるでしょう。
コストバランスの調整
どれだけ気を付けていても、市場のニーズやトレンドの変遷、商品やサービスをリリースするタイミングなどにより、どうしてもカニバリが発生することがあります。そのような場合には、新規事業と既存事業のコストバランスや売上見込みを予測した上で、成長可能性が高い事業にリソースを割き、戦略をシフトする柔軟性が求められます。
また、カニバリを対策するには、市場の流れを読む力だけでなく、サンクコスト(すでに使ってしまい回収の見込みがないコスト)に惑わされず、できるだけ早く損切りする決断力も必要です。
【補足】カニバリを活用する戦略もある
カニバリは一般的にリスクとして捉えられがちですが、実は意図的に発生させることで、事業成長や競争力の強化につながる場合もあります。
ここからは、カニバリを戦略的に活用する方法について具体的に解説します。
自社の市場シェアを拡大する
カニバリゼーションを戦略的に活用することで、自社の市場シェアの拡大を狙うことが可能です。例えば、同じカテゴリに異なる価格帯や特徴の商品を投入することで、多様な消費者ニーズに応え、市場での自社製品占有率を高める、といった具合です。
具体例として、食品業界では、多様なフレーバーの商品を展開することにより、棚スペースを自社製品で埋める戦略が典型的です。ただし、このような方法は、全体の収益向上につながるかどうかを十分に分析してから実施する必要があります。
競合他社との間でカニバリを起こす
カニバリを防ぐだけでなく、競合他社との間で意図的に競争を生むのも戦略のひとつです。例えば、新たな市場に参入することで、競合他社の商品が売れなくなるような状況を作り出す戦略は、あらゆる業界において普遍的に使われています。
また、競合製品と類似したスペックを持つ製品を投入し、価格競争に持ち込む戦略などは、意図的なカニバリゼーションでマーケットを掌握する典型的な手法として知られています。
社内で競争意識を高める
ドミナント戦略の一環として、同一地域内の店舗間で独自の商品開発やサービス改善に努めることで、結果的に全体の競争力を高めるケースもあります。例えば、コンビニエンスストアの各店舗が地域特化型の商品を展開し、そのエリア特有のニーズに応えることで、新たな顧客層を獲得する試みが、これに当たります。
社内の競争意識の向上は、組織全体のモチベーションを高め、ブランド価値の向上や収益拡大といった効果に期待できます。
まとめ
カニバリゼーションは、自社の商品やサービスが競合することで発生し、経営資源の枯渇や競争力の低下といった、深刻なリスクをもたらします。カニバリのリスクと対策をしっかりと理解し、ビジネスの成長と市場優位性の維持に資する戦略を立てましょう。
関連ページ