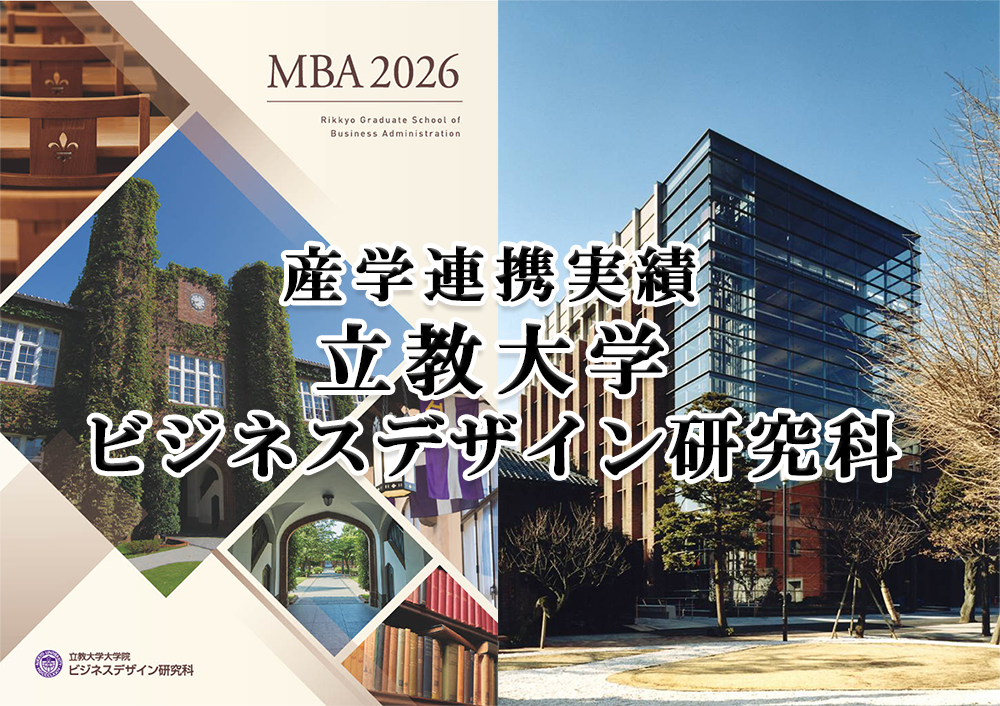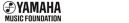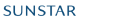データの質を高める柔軟なカスタマイズで、学術研究に最適化されたオンライン実験を実現

学術研究においては、調査設計の精度と収集データの信頼性が研究成果を左右します。中央大学研究開発機構の久徳康史教授は、「So-so psychology」という独自の研究テーマのもと、日常生活における心理的バランスについて研究されてきました。2011年からクロス・マーケティングのネットリサーチを活用して学術調査を実施し、図形認知課題などを通じて人間の心理と行動の関係性を解明する研究に取り組んでいます。
今回は、アンケート画面のカスタマイズ性を活かした学術調査の内容と、その成果について取材しました。
お客様のご紹介

- 1885年創立の英吉利法律学校を前身とする総合大学。現在では8学部・大学院8研究科 などを擁し、建学の精神「實地應用ノ素ヲ養フ」を発展させた「行動する知性。-Knowledge into Action-」をユニバーシティ・メッセージとして掲げ、多様な分野で社会に貢献できる人材を育成している。

(現職・国際経営学部 教授)
プロジェクト概要
課題
- 作業の意義付けが生産性や心理状態に与える影響を客観的に測定したい
- 不正回答や不適切なデータを検出・排除する方法が必要だった
取り組み
- クロス・マーケティングの柔軟なカスタマイズを活用したオンライン実験を設計
-
図形配置のランダム化や画像活用による不正防止対策の実装
- 反応時間や正答率の精密測定が可能なシステムの構築
効果
- 複雑な調査設計への対応により、オリジナルの研究課題を正確に測定できた
- 効果的な対策により、高い品質のデータが得られた
Interview
高い理想を追求するのではなく、日常生活のバランスに着目した心理学研究
――中央大学研究開発機構について教えてください。
久徳 康史教授(以下、久徳教授) 中央大学研究開発機構は、外部資金を活用して社会貢献や産学連携などの研究を推進する機関です。1999年に設立されたもので、当時としては国公立も含めて非常に先進的な取り組みでした。特徴としては、研究ユニット制度の導入が挙げられます。この制度により、条件を満たす資金を確保できれば設置申請書を審査の上、ユニットを立ち上げて研究者が活躍できる場を創出できるようになっています。私もその一員として、機構教授という立場で研究に取り組んでいました。
――久徳教授の研究テーマについてお聞かせください。
久徳教授 現在、私が取り組んでいる主な研究テーマは「So-so psychology」と名付けた心理学の領域です。これは実験心理学の手法を用いて、人が日常生活で感じる安心感と不安感のバランスを探究するものです。多くの心理学研究が高い満足感や幸福感を追求する一方で、私の研究では日々の困難をいかに「ぼちぼち(so-so)」と乗り越えていくかという、より現実的な心理メカニズムに焦点を当てています。
もう一つの軸として企業との共同研究では、実験心理学の手法を用いた消費者心理学の研究も行っています。マーケティングとは異なりますが、消費者のブランド認識や施策の効果検証などが主な内容です。
国際的な評価を受けた共同研究の実績が生み出す、継続的な信頼関係
――クロス・マーケティングとのお付き合いのきっかけを教えてください。
久徳教授 クロス・マーケティングとのお付き合いは、2011年の東日本大震災に関する研究プロジェクトから始まりました。当時、震災後の心理的適応に関する調査を計画しており、私たちが研究デザインを作り、クロス・マーケティングにデータ収集を依頼するという体制で共同研究をスタートさせたのです。
その研究はおかげさまで、2013年にホノルルで開催されたアメリカ心理学会にて、「BEST POSTER AWARD次点」をいただくことができました。それ以降、調査の際にはクロス・マーケティングに多く依頼しています。
――今回はどのような調査を実施されましたか?また、実施された背景や目的もお聞かせください。
久徳教授 今回の調査は「So-so psychology」に基づき、人々が日常的な困難にどう対処するかを調査しています。特に、仕事や課題に対する意義付けが人々の行動や心理状態にどのような影響を与えるかを明らかにすることを目指し、調査を実施しました。
具体的に行ったのは、図形の数を数えるという単純作業です。これは単に注意力と数を数えるという認知的能力を使う作業ですが、それに「意義がある」あるいは「意義がない」と言われたときに、人々の反応がどう変わるかを調査しています。反応時間の速さ、正答率、ポジティブな感情やネガティブな感情の変化といった指標を測定しました。結果の詳細は現在分析中ですが、「意義があればいいものではない」ということが見えてきています。

※実際のアンケート回答画面
学術調査に最適なカスタマイズ性で、精度と信頼性を両立する調査を実現
――今回の調査を進める上で、特に重視したポイントはどのようなものですか。
久徳教授 学術研究においては、不正回答の排除と信頼性の確保が極めて重要です。クロス・マーケティングは不正回答についても透明性をもって情報提供してくださるため、研究の質の向上に貢献いただいています。具体的には、順序効果を取り除くための工夫や、同じような質問を微妙に変えて配置する方法、自由記述回答を活用して不適切な回答者を特定するなどの手法を取り入れました。
また、データの信頼性については、質問紙法では確立された方法論がありますが、行動データでは十分に検証されていないことが多くあります。今回の調査では反応時間や正答率について、信頼性の検証が可能な形式でデータを取得することができました。
星 クロス・マーケティングとしては、回答者の不正防止とバイアス排除を重点的に取り組みました。図形の個数を数える課題では、回答者ごとにランダムに図形の配置が変わるよう設計したほか、テキストではなく画像形式を採用することでブラウザのページ内検索(Ctrl+F)で「×」や「+」がヒットしないようにするなどして不正行為を防止する対策を講じています。調査の相談段階から研究者の立場になって考え、回答の偏りを最小化する配慮を行いました。
鴇巣 学術調査特有の課題として、良質なデータの確保と回答者の負担のバランスがあります。論文の作成に必要な要素をすべて盛り込んでしまうと、回答者の負担が大きくなってしまい、回答の質の低下を招いてしまうのです。そこで、久徳先生との綿密な打ち合わせを通じて、研究の核心部分を損なうことなく、回答者が適切に課題に取り組める環境を設計することに注力しました。この点が学術調査特有の難しさであり、私たちの専門性が発揮される領域だと考えています。
三本柱の研究テーマで日々の生活の質向上に貢献していく
――今後取り組まれる研究テーマや方向性をお聞かせください。
久徳教授 大きな方向性としては「So-so psychology」、「安心感」、「消費者心理学」という三本柱で研究を進めていくつもりです。特に適切な安心感の水準とは何か、完全なリスク回避は非現実的であるという前提のもと、最適なバランスを探究していきます。また、日常的な困難を効果的に克服するための心理的メカニズムの解明は、これからもライフワークとして続けていきたいテーマです。今後は国際経営学部に異動する予定なので、消費者心理学にも引き続き取り組み、企業との共同研究も積極的に進めていきたいですね。
――クロス・マーケティングに対するご意見、ご評価をお聞かせください。
久徳教授 クロス・マーケティングのサポート体制については非常に高く評価しています。迅速なレスポンスに加えて、予算の相談やスケジュール調整も柔軟に対応していただけるので、大変助かっています。さらに、学術調査特有の精緻な調査設計への対応力も優れており、技術的に困難と思われる要望にも的確に応えていただけるので、非常に信頼できるパートナーです。
また、研究予算の効率的な活用という観点からも、適正な価格設定は重要な要素となっています。学術研究費は有限であるため、費用対効果の高いサービス提供は大変ありがたいです。今後も様々なテーマで研究を進めていきますので、引き続きご協力いただければ幸いです。



.jpg)