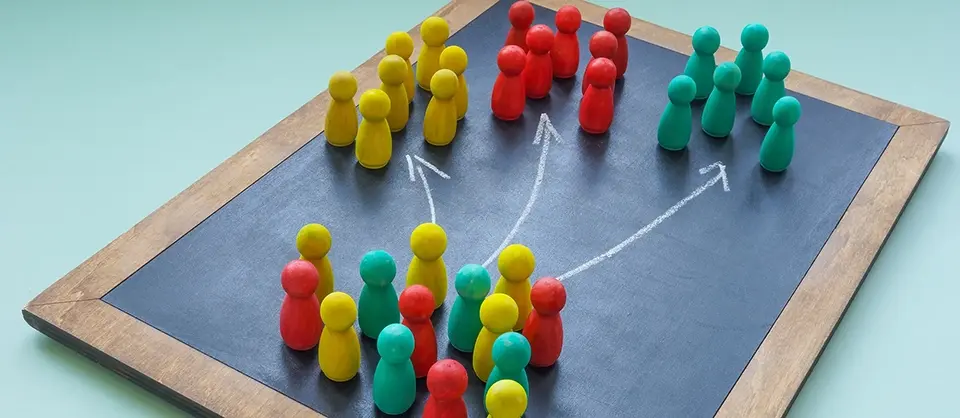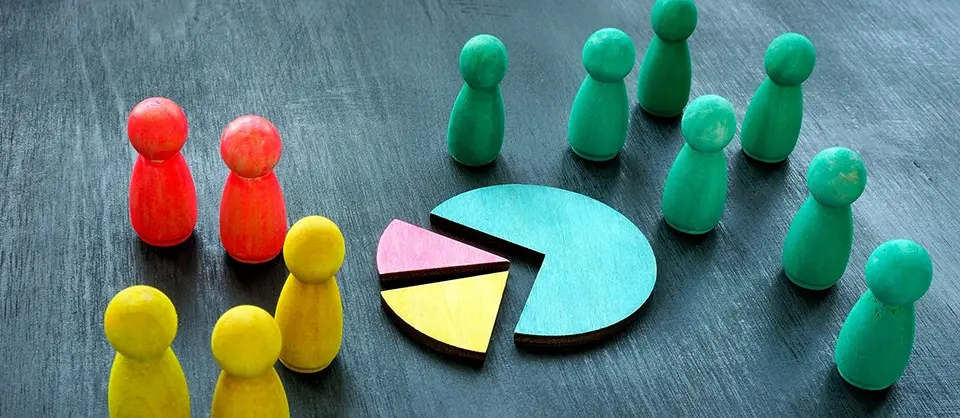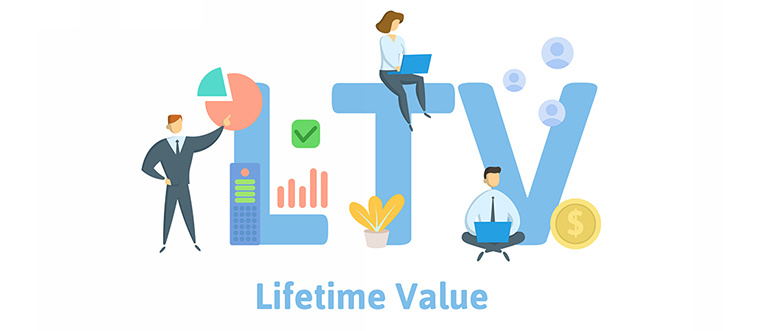CXを向上させる「ブランド体験」の実践 顧客セグメント別の最適なコミュニケーションとは【データマーケ ウェビナーレポート】
公開日:

ウェビナー登壇者情報

株式会社クロス・マーケティング
データマーケティング部 マネージャー
峯俊 洸大

株式会社ファン・マーケティング
コンサルティングチーム チーフ / 自社マーケティング責任者
石田 茉莉子 様
今回は、Braze株式会社主催の「Customer Engagement Days 2025」に登壇した際のウェビナー概要をご紹介します。ウェビナーでは株式会社ファン・マーケティング様と共催で、「CXを向上させる「ブランド体験」の実践 顧客セグメント別の最適なコミュニケーションとは」についてお話ししました。顧客セグメントに応じた最適なブランド体験の定義と施策化についてご紹介したウェビナーで、CX・CRM戦略や顧客コミュニケーション改善に取り組む皆様のお役に立つ内容になっていますのでぜひお読みください。
顧客セグメンテーションと最適な「ブランド体験」の提供
石田様 まずは本セッションの前提を軽く説明いたします。
峯俊 今回のテーマは、顧客セグメンテーションを行い、それに対し最適なコミュニケーションを実施した上で、ブランド体験をしていただくという内容になっています。皆様もご認識の通り、顧客セグメンテーションの重要度はますます高まっていると言えるでしょう。ニーズは多様化し、様々なデータが取得可能になり、そして何より施策の効果を重視する風潮があるかと思います。
しかし、こうした取り組みにおいて、つまずかれる方も多いのではないでしょうか。例えば、「セグメンテーションはできたけれども、そのセグメントに対して具体的にどのようなコミュニケーションを取れば良いのか」という課題です。私たちは、「どのようなコミュニケーションを行うべきか」という点を、「ブランド体験をどう提供するか」という文脈で捉え、支援をさせていただいております。
そうなりますと、私たちが提供している「ブランド体験」の定義が重要になります。それは「属性」「行動」「感情」の3要素から構成される、エントリーから定着までの体験と定義しています。セグメンテーションによって「属性」を把握でき、データによって「行動」も追跡できますが、重要なのは「体験」そのものです。「行動」の中で顧客がどのような感情の変遷を辿ったか、どのような感動や評価があったか、といった「感情」の部分を理解することです。
さらに重要なのは、それらを踏まえてコミュニケーションのあり方を「顧客ドリブン」にすることです。言い換えれば、企業側の都合や「こうしたい」という考えを押し付けてはならない、ということです。私たち2社は、こうした前提に立ち、ご支援をさせていただいております。
ですので、今回は、各セグメントにおける顧客のブランド体験を定義し、施策に落とし込む支援を行っている私たち2社から、まずどのようにセグメンテーションを行い、そのセグメントに対してどのようにブランド体験を定義し、施策に落とし込んでいくべきか、その具体的なアプローチについてお話ししたいと思います。
石田様 峯俊さんありがとうございます。特に先ほどのお話にあった「感情」の部分や、「顧客ドリブン」で進めるという考え方は、非常に重要な前提となります。これを踏まえた上で、「セグメント別にどのようにコミュニケーションを設計していくか」について、2社からそれぞれ異なる切り口や粒度でお話しできればと考えております。

【実践1】N1起点の行動・意識分析によるブランド体験設計
(株式会社クロス・マーケティング)
峯俊 はじめにクロス・マーケティングの手法からご紹介します。
弊社のセグメンテーション手法の特徴は、「N1顧客の具体的行動からの発想」に基づいている点です。まずセグメントを作成し、そのセグメント内にいる顧客一人ひとりの具体的な行動を時系列で見ていくことで、「このような行動をしている顧客は優良顧客なのではないか」といった仮説を構築していきます。
1.星取表(RFM分析視点の応用)による顧客セグメント作成
有効な顧客のセグメントを作るために、RFMの視点を応用した星取表という手法を使っています。星取表では、ある期間ごとに購買が発生したか否かでセグメントを作成し、その顧客セグメント別に人数構成やLTVを確認することができます。お客様の業態に合わせて、例えばオムニチャネルで販売している場合は星取表の観点に店舗利用やEC利用といったチャネルの区分を追加したり、1年ごとに購入金額が上がったか下がったかでセグメントを作成したりします。

2.個票分析によるN1顧客の行動理解
着目すべきセグメントを特定した後には、そのセグメントに属する顧客の「個票」を作成し、購入行動を確認します。マクロデータだけでは見えない個々の購買パターンやサイト利用状況などを読み解き、「このような行動をしている人が優良顧客なのではないか」「この行動がキーになるのではないか」といった仮説を見つけ出す作業を行います。そして、実際にそうした行動が定着率向上につながることが確認できれば、行動に基づいて独自セグメントを作成します。これが、私たちが考える「独自セグメント」となります。

3.顧客理解を深めるインサイトリサーチ(デプスインタビュー・Webアンケート)の実施
次に行うのが、顧客に対するリサーチです。行動データだけではブランド体験の解像度が粗くなりがちですので、行動の前にあるきっかけや、行動の後に得られた評価や感動を明らかにするために、調査を実施します。独自セグメントの顧客に対してデプスインタビューをすることで深掘りを行い、さらにWebアンケート調査などで仮説の検証や定量的な裏付けを取ることで、リアルな顧客体験を定義していきます。

4.ロイヤル化を促す顧客体験ジャーニー定義とCRMコミュニケーション設計
このように収集した行動データと意識データを統合し、顧客がロイヤル化に至るジャーニー=”勝ちパターン”を描き出すことで、各段階で取るべきコミュニケーション施策が明確になります。例えば、「SNSでの投稿を見て話題になっていたので行きました」という声が多く聞かれたのであれば、SNSでの情報発信を強化します。顧客が「このような体験を経て優良顧客になった」という成功パターンを最大限重視し、それに合わせたコミュニケーションを設計していくことを心がけていきます。その際、単に施策を洗い出すだけではなく、事業全体の状況を踏まえた施策の優先順位を決定することも重要です。

5.中間KPI設定による施策効果測定とPDCAサイクルの実現
さらに私たちが重視しているのが、設計したコミュニケーション施策が本当にうまくいっているかを評価するプロセスです。施策が機能した際にどの数値が動くべきか、というKPIをお客様と議論しながら事前に設計しておきます。
ここでも、私たちの特徴である「行動×意識」で捉える視点が重要になります。コミュニケーションの成果を測る上でも、「意識」データが鍵となるということです。顧客の満足度や認識の変化などをアンケートで測定し、それを中間KPIとして設定することで、施策の短期的な効果を捉えることが可能になります。この中間KPIを設定することで、たとえLTVのような長期的な指標がまだ向上していなくても、「LTV向上に向けて重要視しているこの中間指標は、狙い通りに推移しています」と社内で共有しやすくなり、施策成果の報告が格段に行いやすくなります。
「行動×意識」で捉えるアプローチは、お客様からもご好評いただいております。これにより新たな発見があり、コミュニケーションの成果が向上したという事例も多くございます。もしご興味をお持ちいただけましたら、ぜひこちらからお気軽にご相談ください。

【実践2】顧客顕在度に応じた心理・行動仮説とコミュニケーション設計(株式会社ファン・マーケティング様)
石田様 ここからは、弊社の取り組みについてご紹介します。
クロス・マーケティング様からは、セグメントを切ってインタビューや調査を行うというお話がありましたが、弊社からは、顧客セグメントを「顕在度」別に分類し、それぞれの心理状態や行動の仮説を立て、そこからコミュニケーションを設計していく手法をご紹介いたします。
1.顧客の「顕在度」によるセグメンテーション
前提として、マーケティングコミュニケーションで成果を出す上で、ターゲットの心理変容をいかに促すかが非常に重要なポイントと考えます。そのためには、セグメンテーションによってターゲットの輪郭を掴んだ上で、さらにその内面、つまり心理状況を理解しておく必要があると考えています。そのためのアプローチの1つとして、顕在度別に分解して考える方法をご紹介します。

2.セグメント別ターゲット心理・行動の仮説構築の例
例えば、Web広告運用を受注したいとします。セグメントとして、業界や会社規模、月のマーケ予算といった会社情報と、担当者の所属や役職などで切っていくだけでは、「だいたいこんな人」というのは分かりましたが、どんな体験を届ければよいのかが考えにくいですよね。
そこで、そのセグメントを顕在度で分解し、心理状況や想定される行動の仮説を立てていきます。例えば、顕在層は「Web広告の実施を決定している人」、準顕在層は「実施を検討している人」、潜在層は「課題はあるけど具体的な施策には行きついていない人」という具合に分けられます。そして、顕在度ごとに、それらの人がどのような気持ちで何を考え、どのような行動をするのかを考えてみます。
例えば、顕在層(Web広告の実施を決定している人)は、どこの会社に依頼しようか考えていると想定できるので、行動としてはWeb広告の会社を調べたり、費用とサービス内容を比較検討したりすると思います。一方で、準顕在層は実施を検討している段階なので、Web広告以外の他の施策と比較したり、媒体の特徴を調べるといった行動をすると考えられます。潜在層はなんとなく課題感があるものの具体的には考えられていないので、能動的に情報収集するというよりは、流れてきた情報で目に留まったものを見てみるといった行動をすると想定できます。
このように、顕在度によって心理や行動が変わるので、当然とるべきコミュニケーション施策も変わります。たとえば、顕在層は会社名を検索してサービス内容を比較していそうなので、顕在KWでリスティング広告を出したりSEO対策を行い、端的にサービスの特徴や強みを訴求したほうがよさそうですよね。

では、こうした仮説をどのように立てるか、という点ですが、クロス・マーケティング様にご紹介いただいたデプスインタビューや購買データ分析に加えて、Webサイト上での行動分析も有効です。MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入していれば、Webサイト上での個々のユーザー行動が把握できるため、それらのデータから仮説を立てたり、既存の仮説の妥当性を検証したりすることも可能です。

3.5つの要素の一貫性を意識したコミュニケーション設計
ここまで、セグメントを切り、さらに顕在度別に心理や行動を考える、という部分についてお話をしてきました。ブランド体験という観点では、この先の「実行」フェーズが非常に重要ですので、その点について少しお話ししたいと思います。というのも、顧客が最終的に触れるのは、広告やコンテンツといった個々のクリエイティブです。そのため、どんなに良い戦略を立てたとしても、実行段階のクリエイティブと一貫性がなければ、意図したブランド体験を提供できず、その価値を十分に伝えきれません。
実行においては、目的・ターゲット・コンテンツ・表現・チャネルという5つの要素の掛け合わせと一貫性が重要だと考えています。これらの要素間において一貫性を欠くと、コミュニケーションがノイズとなり、かえって悪い体験を与えてしまうことにもなりかねません。(具体的な事例の紹介は個別でさせていただきますので、興味がある方はこちらからお問い合わせください)

4.顧客へのメッセージ伝達効果の検証
ただし、こちらの意図した通りに顧客が受け取ってくれているとは限りません。したがって、顧客からのフィードバックを得たり、ABテストで検証したり、あるいはクロス・マーケティング様のお話にもあったように、調査を実施したりするなど、検証プロセスが不可欠です。実行と検証をセットで進めていくことが大切です。
まとめ
石田様 最後に、今回の内容を踏まえて、私たち2社から今回のウェビナーでお伝えしたかった内容をまとめたいと思います。
株式会社クロス・マーケティング
峯俊 まず、私たちからお伝えしたい内容は主に3つです。
1つ目は、「行動」と「意識」の双方のデータを用いて、顧客がたどるブランド体験のルートをしっかりと定義しましょう、ということです。行動データだけで作りがちなところを、意識データも踏まえて精度を高めることが重要です。
2つ目は、そのジャーニーの中で、どのフェーズに注力すべきかを、市場における自社の立ち位置なども考慮した上で見極め、コミュニケーション戦略を考えましょう、ということです。
そして3つ目として、最も重要なのは、施策がうまくいっているかを測定・評価するプロセスです。長期的なKPIだけでなく、短期的な目標を測る中間KPIも設定し、PDCAサイクルを回していきましょう、ということです。
この3点が、弊社からお伝えしたかったポイントになります。
株式会社ファン・マーケティング様
石田様 続いて、私からも3点に整理してお伝えします。
1つ目は、セグメントを切った後、さらにそのターゲットの心理状況や行動について仮説をしっかりと立て、そこからコミュニケーションを考えることが重要である、という点です。
2つ目は、今回のテーマでもあるブランド体験を高めるためには、実際に顧客が触れるコミュニケーションのクリエイティブ表現にこだわることが非常に大切である、という点です。
そして3つ目は、「なぜ」「誰に」「何を」「どのように」「どこで」という5つの要素の掛け合わせを常に意識し、検証しながら施策を進めることが重要である、という点です。
以上が、私からのまとめとなります。
私たち2社からお伝えした内容が、皆様の業務や課題解決のヒントとなれば幸いです。
ウェビナーテーマ:CXを向上させる「ブランド体験」の実践 顧客セグメント別の最適なコミュニケーションとは
実施日:2025年4月
登壇者

株式会社クロス・マーケティング
データマーケティング部 マネージャー
峯俊 洸大
前職の調査会社でマスコミ、広告代理店、CVS、スポーツ団体等、幅広い業界担当のリサーチャーとして経験を積む。 クロス・マーケティング入社後は、クライアントのデータ活用を支援するデータマーケティング業務を担当。データ分析をベースにした顧客のCRM推進からTableau等のBIツールを通じたデータ活用環境の構築まで、複数の業界業種におけるクライアントのデータマーケティングを支援している。

株式会社ファン・マーケティング
コンサルティングチーム チーフ / 自社マーケティング責任者
石田 茉莉子 様
慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、楽天を経てファン・マーケティングに入社。大手企業の新規事業案件に多く携わり、マーケティング戦略から具体施策の設計、実行まで一気通貫で担当。2024年からは自社マーケティング部門を立ち上げ、オウンドメディア、広告、ウェビナー施策を統括。
関連ページ