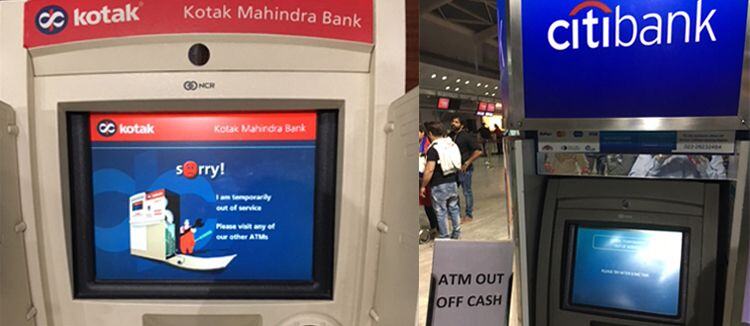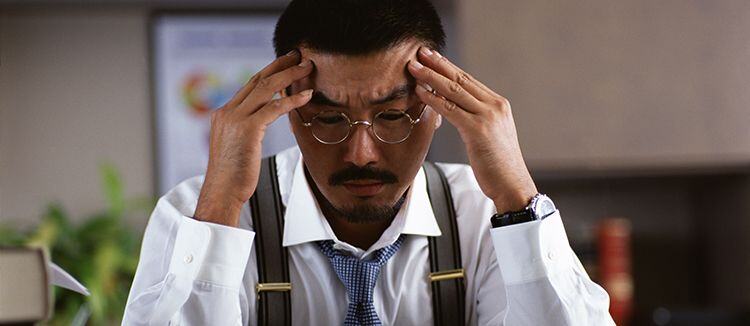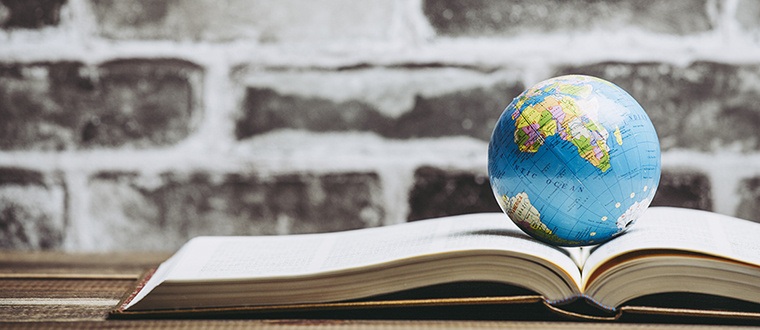グローバルサウス市場における参入戦略立案の具体的方法 vol.1
公開日:


株式会社gr.a.m
常盤 僚平
大学卒業後、日本IBMに入社。戦略コンサルタントとして、総合化学メーカーや大手通信会社を中心に、テクノロジーを用いた事業戦略構築支援、業務改革、システム導入を幅広く経験。
gr.a.mに入社後、日系FMCG(食品・飲料・日用品・化粧品など)企業の海外進出支援を経験。特にアジア市場(東南アジア・中国・インド)を中心に多数の支援実績を有する。
なぜ今「グローバルサウス市場」なのか?日本企業が注目すべき理由と背景
近年、「グローバルサウス」という言葉がビジネスや国際政治の文脈で頻繁に登場するようになっています。これは、アジア・アフリカ・中南米といった新興国・途上国を総称する概念であり、経済成長が著しく、今後の世界経済の中心になると期待されている地域群を指します。従来の「発展途上国」とは異なり、国際社会における発言力や経済的存在感を増しているのが特徴です。
国際連合による「World Population Prospects 2024」によると、2050年には世界人口の約3分の2がグローバルサウスに集中すると予測されています。特に、インド、インドネシア、ナイジェリア、メキシコなどの国々は、人口ボーナスの恩恵を受けて経済成長が加速しており、巨大な中間層の台頭が見込まれています。

出典:国際連合「World Population Prospects 2024」
https://population.un.org/wpp/
日本企業にとっては、国内市場の縮小(少子高齢化・人口減少)に伴い、グローバルサウスへの進出が事業成長の大きな鍵となりつつあります。例えば、ユニ・チャーム、キッコーマン、花王などは、早期から東南アジア市場に進出し、現地化による成功事例を築いています。こうした企業は単に製品を輸出するだけではなく、現地の消費者嗜好に合わせた商品開発、価格設定、プロモーション展開を実施しています。
今後は、FMCGをはじめとした消費財メーカーだけでなく、教育、ヘルスケア、デジタルサービスなどの幅広い分野で、グローバルサウス市場が重要な成長エンジンになると予想されます。
グローバルサウス進出前に必ず行うべき「国別評価」の視点とは?
グローバルサウス進出を考える際、最初に直面する課題が「どの国から着手すべきか」という国別選定の問題です。
ただ、国別に比較するための評価軸は、目的やゴール、制約条件によって変わります。
そのため、いきなりデータの収集から始めるのではなく、まずは現状と現実的な制約条件を加味したゴールを定義し、社内で共有・合意を得てから進出先の選定を行いましょう。
例えば、5年後に1億円の売上を目標とするのか、100億円の売上を目標とするのかでは、進出先、戦略、戦術が大きく変わります。そして、ゴールが明確になった後に、国別評価に進みます。
下記が評価における大まかなステップです。
Step1:市場魅力度の評価
Step2:CAGE分析
Step3:Step1とStep2の結果を元に進出国の決定・進出モデルの検討
Step1:市場魅力度の評価(グローバルサウス市場の潜在力を見極める6つの評価軸)
海外市場に進出する際、単に「人口が多い」「経済が成長している」といった漠然とした情報だけでは不十分です。特にFMCG(消費財)企業にとっては、現地市場の構造や文化、インフラを精緻に把握することで、成功確率の高い国を選定し、適切な参入戦略を描くことが求められます。以下では、FMCG製品の海外展開において市場ポテンシャルを多角的に評価するための6つの軸をご紹介します。
1.人口規模と成長率:購買層の厚みを測る基本指標
市場の基礎ボリュームを把握するには、人口構成と成長率が最も基本的な指標となります。特にFMCG市場では、若年層比率が高い国ほど将来的な消費意欲が旺盛である傾向があります。また、都市部の人口成長率も重要な要素であり、流通や販促の効率化につながります。
参考データ:国連人口統計、World Bank、国勢調査など。
2.都市化率:モダントレードの可動性を左右する要素
都市化の進展は、近代的な流通(モダントレード=MT)や小売チャネルの整備度合いを示します。都市人口の割合やメガシティの存在は、FMCG製品が市場に浸透するうえでの重要な指標です。
例:インドネシアの都市化率は約57%。都市と農村では消費スタイルが大きく異なるため、進出前に確認が必須です。
3.世帯のFMCG消費支出:実際の消費余力を把握
どれだけの金額がFMCGカテゴリー(食品、飲料、日用品など)に使われているかを確認することで、市場の“実力”が見えてきます。カテゴリ別の支出割合や所得層ごとの消費傾向も分析対象になります。
参考データ:Euromonitor、Nielsen、家計調査、World Bank など。
4.流通インフラ:製品が届く仕組みの有無
いかにして製品を効率的に消費者に届けるかという視点も欠かせません。モダントレード(スーパーマーケットやコンビニ)の普及率や、伝統的小売(TT)の規模と機能、卸業者との連携状況などを把握することが重要です。
MT比率の低い国では、棚取りや販売促進費が重要なカギを握り、TT中心の国では現地パートナーの選定が極めて重要です。
5.規制環境:思わぬ障壁を見逃さない
現地の制度面も慎重に調査すべき領域です。価格規制や表示義務(例:Halal認証)、関税・非関税障壁(検疫、通関の遅延)など、参入・販売のハードルを事前に把握することで、トラブルやコストの増大を回避できます。
参考データ:JETRO、WTO、各国商務省、世界銀行データベースなど。
6.文化的親和性:製品と現地の好みの一致度
最後に、自社製品が現地消費者の嗜好や使用習慣にどれほどマッチするかも、成功を左右する要素です。味の好み、使用場面(毎日/特別な時のみ)、ブランド認知など、消費者インサイトを丁寧に調査する必要があります。
インタビュー調査やSNSリサーチ、競合商品の成功/失敗事例からヒントを得るのが効果的です。
これら6つの軸は、FMCG企業が海外進出を検討する際の「市場ポテンシャル評価フレームワーク」として活用できます。複数国を同一基準で比較し、自社にとって最適なターゲット市場を選定するための出発点となるでしょう。
Step2:CAGE分析
市場の成長性だけを見て進出国を決定するのはリスクが高く、制度や文化、距離など多面的に評価することが重要です。
その際に役立つのが「CAGE分析」です。これは、Culture(文化的距離)、Administrative(制度的距離)、Geographic(地理的距離)、Economic(経済的距離)の4軸で、進出国と本国の隔たりを可視化するフレームワークです。

例えば、東南アジア諸国は文化的距離や地理的距離が比較的小さく、日本企業にとっては適応しやすい地域です。一方で、中南米やアフリカ諸国では制度的・経済的な距離が大きく、参入障壁となる可能性があります。
加えて、進出候補国の規制リスク(関税、成分規制、外資規制など)やディストリビューターの有無・質も重要な判断材料になります。こうした評価軸を用いて、複数の国をスコアリングし、段階的に優先順位をつけるアプローチが有効です。
このような体系的な国別評価により、失敗のリスクを抑えつつ、自社の強みが活かせる国から着実に進出していくことが求められます。
Step3:Step1とStep2の結果を元に進出国の決定・進出モデルの検討
以下に、日本企業が進出を検討することの多い3カ国(インドネシア、インド、ブラジル)について、CAGE分析の結果と参入形態の示唆を整理します。

【インドネシア(総合距離スコア:8|距離が近い)】
市場魅力度:高
参入形態(例):
比較的文化・地理的距離が近く、親日的な雰囲気もあるため、初期の進出先として好適。モダントレードの整備も進んでおり、直販や現地法人による展開が現実的。
→ 推奨戦略:優先参入市場。直販+スーパーマーケット(MT)展開。
【インド(総合距離スコア:12|中距離)】
市場魅力度:非常に高い
参入形態(例):
人口と消費力のポテンシャルが非常に高いが、制度面や文化的習慣にギャップあり。いきなりのフル参入ではなく、信頼できる代理店との連携を軸に段階的に市場理解を深めていく戦略が必要。製品も現地適応が鍵となる。
→ 推奨戦略:代理店経由での段階的進出+現地向け製品開発。
【ブラジル(総合距離スコア:15|距離が遠い)】
市場魅力度:中
参入形態(例):
言語・制度・物流面の壁が大きく、リスク分散の観点からも「輸出型モデル」や現地パートナーとの連携が現実的。また、日・メルコスールFTAの条件や関税障壁の事前確認が不可欠。
→ 推奨戦略:リスク分散型の輸出モデル。FTA条件確認が必須。
まとめ
このように、CAGEスコアと市場魅力度を掛け合わせることで、「どの国から入るべきか」「どのような形態で進出すべきか」「どの程度の投資を許容すべきか」といった判断が構造的に行えるようになります。単に魅力がある国=参入すべき国、ではなく、「自社が適応しやすい国」を見極めることが、グローバルサウス戦略成功の鍵を握ります。<会社概要>
株式会社gr.a.m
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
03-6859-2252
※「海外情報ナビ」https://global-biz.net 運営会社
関連ページ